「AIはどこまで”考えて”コードを書けるのか?」
「このコード、あとから書き直したくなるな…」
もしあなたがプログラミングに挑戦したことがあるなら、こんな経験があるのではないでしょうか。
コードを書く作業は、まるで家を建てるようなもの。
土台を作り、壁を立て、屋根をつける…と思いきや、途中で設計図を変えることもしばしば。
枠を作っては戻り、時には土台からやり直す。
そんな”行ったり来たり”が当たり前の世界です。
では、AIはどうでしょう?
これまでの多くの生成AIは、まるで巻物を書くように”左から右へ”一方向に文章やコードを生成してきました。
けれど、コードという設計図を組み立てるには、もっと柔軟に、行ったり来たりできる”考える力”が求められます。
そこで登場したのが DiffuCoder です。
Apple と香港大学の研究者たちが開発したこの新たなコード生成AIは、これまでの常識を覆しました。
コード生成に革新をもたらす「拡散モデル」とは?
従来のAIが採用していた「オートレグレッシブモデル」とは、左から右へと一文字ずつ順番に生成していく仕組み。
例えるなら、一本道をただひたすら進むランナーのようなものです。
しかし、DiffuCoder が採用したのは「拡散モデル」。
これは、完成図のすべてを”ぼかして”しまい、そこから徐々に”はっきり”と再構成していく手法です。
たとえるなら、霧の中から浮かび上がる写真を、少しずつピントを合わせながら仕上げていく感覚。
この手法の革新性は”順番通り”にこだわらず、必要な部分から自由に埋めていけること。
だから、コード生成でも”戻ったり””飛ばしたり”といった、人間に近い柔軟な動きが可能になるのです。
DiffuCoder が見せた、新たな可能性
研究チームは、1300 億のコードトークンで学習した7Bパラメータのモデル「DiffuCoder」を開発し、その特性と効果を徹底的に分析しました。
分かったことは──
- 拡散モデルは、生成順序を自ら”選べる”
- 温度(生成の多様性)を上げることで、選ぶ単語だけでなく生成する順番までも変化する
- この多様性が、より良いコードにたどり着くための”探索の幅”を広げる
さらに、強化学習(RL)と組み合わせた新手法「coupled-GRPO」も開発。
これにより、コード生成ベンチマークで 4.4% の性能向上 を実現しました。
まさに、AIが”考え、試し、学び直す”力を手に入れた瞬間です。
私たちが学べること
DiffuCoder の研究は、私たちにこう語りかけています。
「AIもまた、”考える順番”を自由にできれば、もっと創造的になれる」
これは、まるで人間の思考そのもの。
アイデアを試し、戻り、時には大胆に変えてみる──そんな柔軟さが、これからのAIにこそ求められているのかもしれません。
DiffuCoder は、コード生成の未来だけでなく、AIの進化そのものに新たな一歩を刻みました。
あなたが次にコードを書くとき、もしくはAIと向き合うとき──
その背後に、じっくり”考える力”を持ったAIがいることを、ぜひ思い出してみてください。
もしかしたら、あなたの創造力も、ひとつ先のステージへと進むきっかけになるかもしれません。
参考:DiffuCoder: Understanding and Improving Masked Diffusion Models for Code Generation
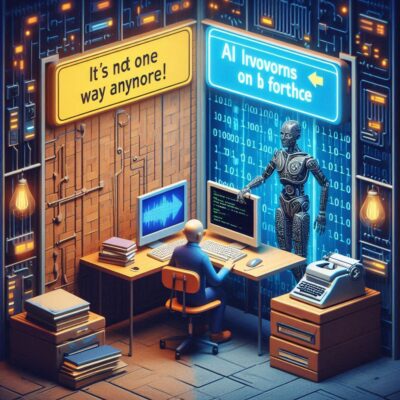
コメント