ある日突然、健康だった人が深刻な病に倒れる――。
膵臓がんは、まさにそんな「静かなる殺し屋」とも呼ばれる病です。
自覚症状が現れにくく、見つかった時にはすでに手遅れ。
医師たちをして「発見が最も難しいがんの一つ」と言わしめるこの病に、ある企業が挑戦を始めました。
その企業とは、私たちがよく知る「写真とフィルムの会社」――富士フイルムです。
けれど、今回の主役はカメラではありません。
最先端のAI(人工知能)技術を搭載した超音波内視鏡なのです。
なぜ「膵臓がん」は見つけにくいのか?
まず、なぜ膵臓がんはこれほどまでに「厄介」とされるのでしょうか?
膵臓は、胃や腸の奥深くに隠れた臓器です。
一般的には体表から超音波診断装置を使ったり、CT(コンピューター断層撮影装置)で撮影したりすることが多いのですが、精密な検査には限界がありました。
また、初期段階ではほとんど症状が出ないため、気づかないまま進行してしまうケースが大半なのです。
その結果、胃がんや食道がんなどに比べて生存率が低く、国内では年間約4万人が命を落としています。
富士フイルムの革新的アプローチ:「内側から」膵臓を見る
では、どうすれば早期発見が可能になるのでしょうか?
富士フイルムが着目したのは「口から胃に通した内視鏡の先端から超音波を当て、内側から膵臓を調べる」という手法です。
しかし、この超音波内視鏡による検査は、これまで熟練した医師でなければ難しいものでした。
そこで開発されたのが、AIが検査中の医師に対し、画面上のどこに膵臓がありそうかをリアルタイムで知らせるシステムです。
病気の疑いがある箇所には枠囲みをして、医師にアラートをしてくれます。
医師の技術格差を埋めるAIの力
このAIは、既に胃や大腸向けで発売済みの内視鏡AIシステム「CAD EYE(キャドアイ)」の新機能として提供されます。
これまで熟練の医師の技術に頼っていた高度な検査を、AIがサポートすることで誰でも実施できるようになる。
医療の地域格差を縮め、救える命を増やすことができる。
そんな未来が、いよいよ現実のものになろうとしています。
2025 年、医療の風景が変わる
このAI搭載超音波内視鏡は、厚生労働省から薬事承認を取得し、2025 年内にも発売予定です。
超音波内視鏡による膵臓の診断支援に使うAIが薬事承認されるのは、富士フイルムが初めてとなります。
「写真技術と医療技術の融合」という富士フイルムの強みが、命を救う新たな一手となるのです。
終わりに:未来を変えるのは、技術だけじゃない
技術の進歩はもちろん素晴らしいことです。
けれど、それを支えているのは「誰かを救いたい」という人間の想いです。
富士フイルムの取り組みは、まさにその証でしょう。
かつてフィルムで「一瞬を残す」ことに挑んできたこの会社が、今度はAIで「未来を守る」挑戦をしています。
私たち一人ひとりの命の価値を、技術がやさしく支えてくれる――そんな時代が、もうすぐそこまで来ているのです。
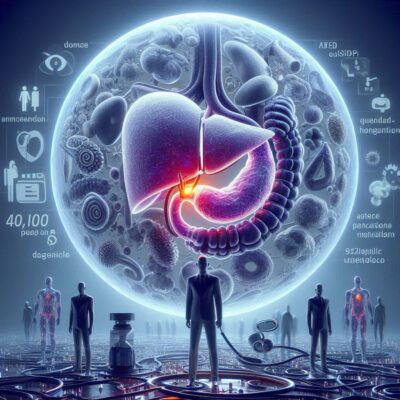
コメント