AIが医療現場に導入されるようになって、私たちは多くの恩恵を受けるようになりました。
画像診断の精度が向上し、見逃しが減る。
スピードも正確さも、人間だけの作業では追いつけなかった部分を補ってくれる。
まさに頼れる「パートナー」としてのAI。
でも、頼りすぎたらどうなるのでしょうか?
今回ご紹介する研究は、そんな私たちの「AIとの付き合い方」に一石を投じる、非常に興味深い内容です。
テーマは、大腸内視鏡検査におけるAIの”副作用”。
なんと、AIが医師のスキルを徐々に奪ってしまうかもしれないというのです。
見逃さないためのAI、それが逆効果に?
研究を行ったのは、ポーランドの消化器専門医たち。
対象となったのは、大腸内視鏡検査で腺腫(前がん病変)を発見する能力です。
AIを使えば、微細なポリープも見逃しにくくなり、がんの早期発見につながる—これはすでに多くの研究で証明されており、世界中の病院でAI支援の導入が進んでいます。
しかし今回の研究では、ベテランの内視鏡医がAIを「毎回使う」ことで、むしろ自分の観察力を失いかけているという驚きの結果が出たのです。
2つのグループで比較された結果とは?
研究チームは約6ヶ月間にわたって、2つのグループを比較しました。
- AI支援を常に使った医師グループ
- AIなしで検査を行った医師グループ
その後、両方のグループに「AIなしでの検査」をしてもらい、ポリープの検出率を比べたところ…
なんと、常にAIを使っていた医師のほうが、成績が落ちていたのです。
しかも、経験豊富な医師ほどスキルの低下が顕著だったというのですから、さらに驚きです。
つまり「頼れるから使う」AIが、結果的に“頼らなければ見つけられない体”にしてしまっていたというわけです。
なぜスキルが落ちるのか?
人間の脳はとても柔軟で、便利なものがあるとそれに”最適化”してしまいます。
たとえば、カーナビに頼りきっていたら、地図を読めなくなったり、道順を覚えられなくなったりしますよね。
医療の現場でも同じことが起きている可能性があるのです。
AIが「ここに腺腫がありますよ」と教えてくれるなら、医師は”自分で探す”努力を徐々にしなくなる。
目の使い方、微細な変化を察知する力、判断のための直感—これらはすべて「使わなければ鈍っていく」スキルです。
AIと人間、どう共存すべきか?
もちろん、この研究はAIを否定しているわけではありません。
実際、AIの導入で救われた命もたくさんありますし、今後も重要な技術であることは間違いありません。
大切なのは「AIに頼ること」と「AIに預けすぎないこと」のバランスです。
今回の研究チームも提案しています。たとえば:
- 医師が意図的にAIなしの検査も行うことで、スキルの維持を図る
- 教育や訓練の中でAIに頼らず診る力を育てることに注力する
- AIの提示結果に対し、あえて疑問を持つ習慣を育てる
AIは私たちの「拡張装置」であるべきで「代替装置」になってはいけない。
そうした意識が、これからの医療を支えるカギになるのかもしれません。
まとめ:AIは「助手」であって「主役」ではない
AIは驚異的な速さで進化しています。
そして医療現場においては、今後ますます重要な存在になっていくでしょう。
でも、技術の進歩が人間の直感や経験を鈍らせてしまっては、本末転倒です。
どんなに便利でも、私たち人間が「考える力」や「感じる力」を手放さないこと。
それが、AI時代において本当に必要な”人間らしさ”なのではないでしょうか。
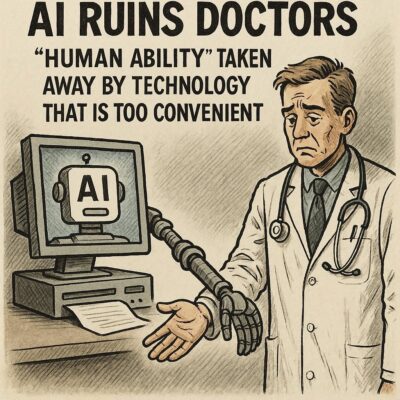
コメント