「AIで会社を変える」は幻想なのか?
「生成AIを導入すれば、生産性も収益も飛躍的にアップする──」
そんな夢のような話を、ここ数年で何度耳にしたでしょうか。
実際、あなたの周りにも「ChatGPT を導入しました」「社内業務にAIを活用中です」といった事例が増えているかもしれません。
でも、心のどこかで思っていませんか?
「で、結局それって儲かってるの?」
この問いに、驚くべき答えを出した調査があります。
MIT メディアラボから派生したAI企業 NANDA が実施した調査によると──
生成AIのパイロットプロジェクトのうち、実際に本格運用に移行し、測定可能な金銭的価値を生み出したのは、たったの5%だったのです。
え?
あれだけ話題になっているのに、95% は効果なし?
いったいどういうことなのでしょうか。
期待と現実のギャップ──でもそこには理由がある
この調査結果を聞いて、がっかりした人もいるかもしれません。
でも、落ち着いてください。
これは「AIが無意味だった」という話ではありません。
むしろ“過度な期待”が先行しすぎただけかもしれないのです。
例えば、ピアノを買ったからといって、いきなりショパンが弾けるわけではありませんよね?
ピアノはあくまで「道具」であり、それを使って何をするかは「人次第」です。
生成AIもそれと同じです。
NANDA の調査は、52の企業意思決定者への構造化インタビュー、300 以上の公開AI取り組みの分析、153 の企業リーダーへのアンケート調査から構成されています。
調査では、生成AIプロジェクトがパイロット段階を終了してから6ヶ月後の投資収益率を測定しました。
なお、この調査については、学術的な厳密性に疑問があり、NANDA 自身がAIサービスを提供する企業であることから、マーケティング的な意図も含まれている可能性が指摘されています。
そのため、結果の解釈には注意が必要です。
5%の成功企業は、何が違ったのか?
では、5%の「AIで収益が大きく改善した」企業は、何をしたのでしょうか。
調査によれば、成功した企業には共通点があります。
- 経営層がAI活用に強いコミットメントを持っていた
- 部門横断的にAIの導入を進めた
- 社員に対する継続的なAI教育を行った
- 目的を「業務改善」ではなく「競争力の再定義」に置いていた
つまり、AIを単なる便利ツールとしてではなく、経営戦略の中核に据えていたのです。
まるで、ピアノを弾くために毎日地道に練習を重ね、音楽家として舞台に立つ覚悟を持った人のように──。
見えない価値が、やがて大きな差になる
もうひとつ見逃せないのが、短期的な利益だけを見てはいけないという点です。
調査では、収益への直接的なインパクトは少なくても「顧客体験の向上」や「社内業務の効率化」など、中長期的な価値創出につながる成果が多数報告されています。
たとえるなら、まだ芽を出していない種をまいたような状態。
すぐに花は咲かなくても、確実に土の中では成長が始まっています。
AIは「魔法の杖」ではない。でも、育てれば未来を変えられる
今回の調査結果が教えてくれたのは「AIは導入すれば勝手に成果を生む魔法の杖ではない」という、当たり前だけれど大切な事実です。
でも同時に「正しい戦略と学びの姿勢があれば、AIは確かに未来を変える力を持っている」という希望も見せてくれました。
5%という数字に落胆する必要はありません。
むしろこれは、これからの 95% に、可能性が眠っているということなのです。
あなたの組織がその可能性を育てられるかどうかは、今後の一歩にかかっています。
── AIを導入することはゴールではありません。
それは、未来を自分たちでつくっていく旅の、ほんの始まりなのです。
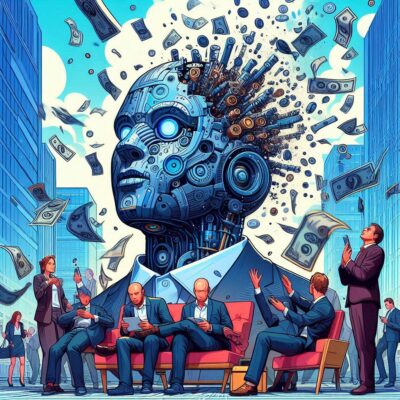
コメント