「AIって、もう人間と同じくらい賢いの?」
「最近、子どもが”AIの先生”に宿題を手伝ってもらってるんです」
―― そんな話を聞いたとき、あなたはどう感じたでしょうか?
便利そう? ちょっと心配?
それとも、未来はもう来ているとワクワクしましたか?
AIが文章を書き、絵を描き、数学の問題を解き、そして人間のように会話する――そんな時代が今、目の前にあります。
でも、ふと思うのです。
「これって、本当に”人間の知能”に追いついているの?」と。
このモヤモヤに答えようとしたのが、2025 年10月に発表された論文『A Definition of AGI』。
この記事では、その内容をかみ砕きながら、AIの進化の本当の「今」を一緒に見つめてみましょう。
AGI は「教養を受けた成人のような思考力を持つAI」
論文が目指したのは「AGI(汎用人工知能)」のはっきりとした定義づけです。
それは――
AGI とは、よく教育を受けた成人と同等の幅広く高度な認知能力を持つAI。
つまり、数学が得意とか、言語に強いとか、そんな「一芸に秀でたAI」ではなく、幅広い領域でバランスよく思考・判断・理解できる”知のオールラウンダー”が AGI、というわけです。
この定義をもとに、研究チームは「人間の知能って何からできているの?」を探る理論として、心理学で最も信頼されている「CHC 理論(Cattell-Horn-Carroll 理論)」に基づいた10の認知能力をピックアップ。
それぞれについて、人間と同じようなテスト項目をAIに課し、定量的にスコア化する―― そんな極めて具体的で実践的なアプローチが取られました。
「得意な記憶、だけど、保てないかも…」AIの力と脆さ
さっそくGPT-4(2023 年)と GPT-5(2025 年)をこの新フレームワークで評価してみた結果――
- GPT-4:AGI スコア 27%
- GPT-5:AGI スコア 57%
「えっ、半分も行ってないの?」と驚くかもしれません。
でも、この数字は単なる「平均点」ではありません。
10の能力カテゴリそれぞれを 10% ずつ配点し、その合計が AGI スコアになるのです。
GPT-5 は「一般知識」「読解と記述」「数学」には強さを見せましたが「長期記憶の保存」「記憶の取り出し」「視覚・聴覚処理」「速度」といった”人間にとっては当たり前”な能力が、ほとんどゼロに近かったのです。
たとえば――
- 会話の流れを長く覚えておけない(昨日話したことは忘れている)
- 聴いたことをリアルタイムで覚えて、再現するのが苦手
- 複雑な図を見て、意味を読み取ったり、関連づけたりできない
まるで、10万冊の本を暗記した秀才だけど、図書館の出口がわからない――そんな印象です。
「いまどのAIの、どこがなぜ足りないのか」
この研究の本当の価値は「何ができて、何ができないのか」を具体的に明らかにした点にあります。
今までは、AIが一部の分野で驚異的な成果を出すと、まるで”人間超え”のように思ってしまいがちでした。
でも、こうして丁寧に分解してみると、AIはある能力で他をカバーしようとする「能力の歪み(capability contortions)」を起こしていることがわかってきたのです。
たとえば:
- 長期記憶がない → だからその都度、大量の文脈を”思い出させる”必要がある(巨大なコンテキストウィンドウで補償)
- 正確な知識が出せない → 外部検索に頼って、なんとか情報をつなぎ合わせている(RAG=検索拡張生成に依存)
こうした「応急処置的な工夫」は”本当の知能”の代替にはなりません。
まるで、何度教えても同じことを聞いてくる優等生のような状態。
便利ではあるけれど「本当にわかってる?」と疑問に思ってしまうのです。
これからの課題、それは「覚えて、学び、成長すること」
AGI を目指すうえで最大のボトルネックは、やはり「長期記憶」――
AIが一度学んだことを、自分の中にとどめて、次に活かせるようになることです。
私たち人間は、失敗や出会い、感情の揺れを通して学びを積み重ねていきます。
でも、AIはいまだに「初対面のまま」。
どれだけ会話を重ねても、次回にはまた一から関係を築き直す必要があります。
AIが「知識」ではなく「経験」を重ねられるようになったとき―― そこには、いまよりもっと深い意味での「知能」が生まれるのかもしれません。
おわりに。AIを「思考の協働者」として
AIは、たしかにすごい存在です。
でも、私たちと同じように「考え」「覚え」「成長する」存在には、まだなっていません。
それでも―― 私たちはこの”未完成の天才”と、これからどう向き合うのかを考える時期に来ています。
AIを道具として見るのか。
それとも、思考のパートナーとして、ともに未来を築く存在とするのか。
『AGIの定義』が描いたのは、単なる技術の進歩ではありません。
それは「人間とは何か」を、改めて私たちに問いかける一枚の地図だったのです。
AIが”賢い”って、どういうこと?
――その答えは、もしかすると私たち自身が”賢く”なろうとする姿にこそあるのかもしれません。
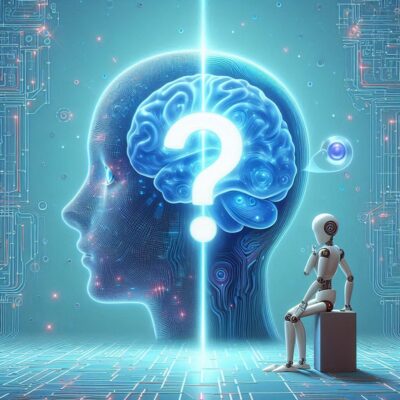
コメント