「使いたい時には、もう遅い」――そんな経験、ありませんか?
新しいツールを試してみたいと思っても、社内の承認フローに何週間、時には何ヶ月もかかってしまい、いざ導入が決まった頃には、すでにそのツールへの熱も冷めてしまっている。
そんなもどかしさを感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
実は、あの急成長中のスタートアップ Brex(ブレックス) も、まさに同じ壁にぶつかっていました。
しかし彼らは、そこで立ち止まりませんでした。
「このままでは、AIの波に取り残される」
そんな危機感から、Brex は従来のやり方を手放し”少し乱雑だけど、本質的な価値にたどり着ける道”を選んだのです。
月単位の導入検証? それ、もう時代遅れかも
Brex はもともと、他の多くの企業と同じように、ソフトウェア導入時には慎重な検証プロセスを踏んでいました。
時間をかけてリスクを見極めることが、安定運用のためには当然とされていたのです。
ところが、ChatGPT 以降のAIツールの進化スピードは、企業の調達サイクルを軽く凌駕してしまいました。
CTO のジェームズ・レッジオ氏は3月の HumanX AI conference で TechCrunch にこう語っています:
「プロセスが完了する頃には、現場のチームがそのツールへの興味を失っているんです」
もはや「検討している間に時代が変わってしまう」。
そんな現実が、今のAIのスピード感なのです。
「正確さより、素早さ」:AI導入の新ルール
Brex はここで思い切った決断をしました。
“完璧な調達”をやめ”早く試してみる”ことを優先する方針に舵を切ったのです。
その具体的な取り組みとして、まずAIツール向けの法務・データ処理の新フレームワークを整備しました。
さらに、社員自身が価値を感じたツールを継続利用する「スーパーヒューマン プロダクト・マーケット・フィットテスト」を導入し、加えてエンジニア一人ひとりに月 $50 のツール選定予算を配布し、承認済みリストから自由にソフトウェアツールを選択できるようにしたのです。
この大胆なアプローチにより、Brex では約2年間で 1,000 のAIツールが社内で利用されるようになり、その中で価値を見極めた結果、5〜10 の大規模な導入についてはキャンセルや更新停止を行ったそうです。
「全員が同じツールを選ばない」ことの価値
興味深いのは、Brex の取り組みにおいて、社員の選択がバラバラであったことです。
レッジオ氏は「全員が Cursor のような特定のツールに殺到するような収束は見られなかった」と語っています。
例えば、特定の人気ツールに全員が飛びつくわけではなく、各自が自分の業務に合ったツールを選び、現場レベルで最適化を進めていったのです。
この「分散型の試行錯誤」が結果的に、実際の利用者数をより正確に把握することで、会社全体でどのツールに本格投資すべきか、より広範なライセンス契約を結ぶべきかを見極めるヒントになったと言います。
完璧な答えなんていらない。「混沌」を恐れず、まず動こう
最後に、レッジオ氏の言葉をご紹介します。
「最初から完璧な判断をしようとしないこと。それが、取り残されないための最大のポイントです。6〜9 ヶ月かけてすべてを慎重に評価してから導入するような考え方は間違いだと思います。9ヶ月後の世界がどうなっているかなんて、誰にもわからないのですから」
私たちはとかく「失敗しないこと」を重視してしまいがちです。
ですが、今のAIの世界では、それがかえって最大のリスクになってしまうのかもしれません。
完璧じゃなくていい。
とにかく一歩踏み出して、試してみる。
その一歩の先に、次の大きな可能性が広がっているのです。
【まとめ】Brex に学ぶ、これからのAIとの付き合い方
Brex の取り組みから見えてくるのは、今のAI進化スピードには従来の導入プロセスはもう合わないということです。
これからは小さく、早く、試すことが新しい成功パターンとなり、完璧主義より柔軟さとスピードがカギとなります。
また、社員に「選ぶ権利」を与えることで現場主導の最適化が進み、混沌の中にこそ本当の価値が眠っていることを彼らは証明したのです。
さあ、あなたの会社でも “ちょっとした実験” を始めてみませんか?
「正しくあろう」とするあまり、何もしないでいるより「間違ってもいいから動いてみる」方が、今はきっと価値がある。
Brex のように、”混沌を抱きしめる勇気”を持てたとき、あなたの組織にも、新しい可能性が見えてくるはずです。
参考:How Brex is keeping up with AI by embracing the ‘messiness’
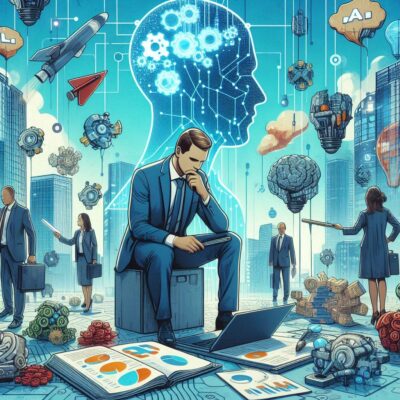
コメント